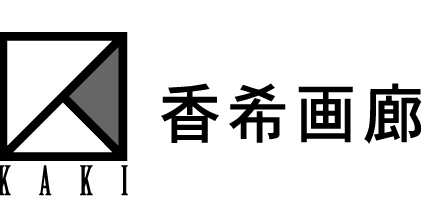Art Column

第11回「蝶のゆくえ」
その絵は母の葬儀の翌日、画廊に届けられた。20年前に93歳で没した高岡市出身の銅版画家、南桂子の油彩画である。絵の裏面に1973年と記されあるので、制作当時南は62歳。カラーメゾチントの技法で世界的に名を馳せた版画家の浜口陽三と、故郷を捨て、遠くパリに暮らしていた。
闇夜をおもわせる黒のグラデーション。画布に絵の具を細かく叩きつけて得られたマチエールに、ぼーと茶色に浮かびあがるのは花なのか、それとも木立か。明快と見えて実は不可解な形象。花芯か、否、木立の中に透けて見える空だろうか、水色を施された中央に、言語を拒絶した蝶が羽をひろげている。
魚津の老人病院に転院していた母の容体の急変を知らせる連絡が入ったのは、その日の仕事も終わった19時を過ぎていた。私は富山から車で夜の街を魚津の病院へと急いだ。移された個室で先に到着した妹が見守るなか、母は苦しそうに喘いでいた。「来たよ。傍にいるよ。」と言うと、溺れる者が何かをつかむようにして、母は布団から私の方に手を伸ばした。苦痛を訴えたかったのか、死への怖れからか、それとも今生の別れを覚ったからなのか。医師は母の状態を説明した後、病院に居てもらう事は出来ないので帰って連絡を待って欲しいと言った。老人病院の規制は未だにどこも厳しい。今この手を振り解いて帰らなければならないのか。このままここ居させてほしいと懇願しようとする私に「規則だから仕方がない、帰ろう」と妹が促した。病院と近い妹の家に一緒に行こうと言うが、そんな気にはなれなかった。拒否する私を置いて妹は帰って行った。私はひとり困惑し、思考は闇夜を彷徨った。
日が変わりまだ暗く明けきらぬ頃、病院からの電話で駆けつけた病室で、すでに母は虫の息だった。母の手を握りしめ、私は辺りを憚ること無く大きな声で母に語りかけた。「お別れの時が来ました。これまで本当に有り難う。妹と仲良く助け合って生きて行くから心配ないよ。有り難う、さよなら。」とそこまで話したら、もう言葉が続かなかった。母に私の声は届いているのだろうか。私は咄嗟に、「ずいずいずっころばし ごまみそ ずい」と幼いころ母がよく歌ってくれた手遊び歌を歌った。と、片目だけ開いていた母の左目に一瞬力が宿ったように見えた。聞こえているんだと、こころを強くして歌を続けたが、最後にもう一度母に有り難うと、さよならを告げた。
南はどんな気持ちであの蝶を描いたのだろう。蝶は、何を求めて、一体何処へ飛んで行くのだろう。現実と非現実の危うい異界を漂うのか。抗ってもいずれは永遠の闇に吸い込まれて消えてしまうのか。覚束なくも明かりに向かって現実を飛び続けて行くのか。あるいは蝶は飛んでさえもいないのか。
残された母の記憶。その記憶はいつか夢か幻のように曖昧になって消えてしまうのだろうか。それとも記憶はその死を凌駕していつまでも私と共に生き続けるのか。
「アインス(eins)ツヴァイン(zwei)ドライ(drei) 進め、進め!」父が死の際にそううわ言を言ったと、最近になって妹が話してくれた。
正直なところ私は今、喪失の悲しみという大きな檻に捕らえられて、生きて行くのが心許ない。
「なるようになる。なるようにしかならない。」よくそう言っていた母の、穏やかな声が聞こえた気がした。