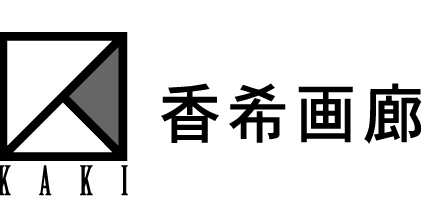Art Column

第31回「往く男」
最後の一葉を落として梢を大空に広げる欅を見上げた。空が明るい。
年暮れに書棚を片付けようと手前にある小箱を手に取った。思いがけず重い。何だろうと紐を解いて蓋を開けたら「萬寿無疆」(ばんじゅむきょう)銅印の書鎮であった。保と箱書があるから高岡の金工作家、般若保氏の作だろう。中に父の字で「平成六年五月拾壱日 香世ヨリ六十七歳誕生日ニ被贈」と書かれた紙が、几帳面に折り畳んで入っていた。私から父へ贈った誕生日プレゼント。にわかに思い出せなかった。父の67歳を祝った私が、今その年になっている。
さて、「萬寿(ばんじゅ)疆(きわま)り無し」。新年を迎えるに際しどの作品を飾ろうかと相談して、ブラマンクの雪景色はどうだろうとなった。油彩の40号の展示はさすがに一人では無理である。二人で掛け、絵から離れてしばし眺めた。「いい絵だね」と相棒が一言呟いた。
教会がみえる雪の道を、冬の日本海を思わせる暗くどんよりとした空の下、ひとり男が歩いている。男はコートも着ていない。少し前のめりで先を急いでいるようにも、一歩一歩ゆっくり歩いているようにもみえる。ほかに人の気配はない。北風が裸木の枝の雪を吹き飛ばし、ただ教会の青い尖塔だけが鈍色の空を差している。はるかに続く雪道と縹渺たる空の境は朧気に明るい。日暮れ近くだろうか、それとも夜明け前か。ペインティングナイフで一気に塗られたジンクホワイトの雪が、冬の空気の清冽さを極めて、どこか悪魔祓いのようでもある。
さて、「芸術は自然を模倣する」という考えに対して、「自然は芸術を模倣する」という警句があるが、これは単なる逆説ではないだろう。すぐれた作品は私達の現実を見る目をかえさせる。例えば北斎が出てから海波が北斎の浪になったように。森の木立を見て思わず「東山魁夷の絵のようだ」と言ったりする。ブラマンクを知ってから郊外はブラマンクの風景になった。
そしてもはや可視的には存在しない風景が明確にあらわされている時、作品は存在するといえる。
目の前にあるブラマンクの絵に描かれた景色は、実在の風景ではないのではないか。雪で白く覆われた道や、不穏な空、歩く男、風雪のなかに聳り立つ教会さえも。否、実在していようと、していまいとそれはどうでもいい事なのだ。何故ならこの絵にブラマンクが描いたのは、あるいは描きたかったのは、「生きて行くとは」という問いかけ、あるいは「生きて行こう」とする勇気なのかもしれないから。「それでも」という逆説の接続詞をともなった。
まっすぐに伸びた道のように思えた人生。若き日はずっと先まで見通せたつもりでいた。ところが現実は紆余曲折、光があれば闇もある。生きることは甘くないと思い知らされて久しい。年を重ねた今、人生を一生の総体と捉えるなら、過去を振り返ったり、現在に拘泥するばかりでなく、行く先にどんな景色が待ち受けているのか、どんな美しさに助けられるのか、想像するのも悪くない。
「曲がり角をまがったさきになにがあるのかは、わからないの。でも、きっといちばんよいものにちがいないと思うの」アン・シャーリー※はそう言った。
しかしブラマンクの絵の中の男にアンのひたむきな明るさは認められない。明け方の夢を引きずっているのか、それとも何かに突き動かされて夕暮れを急いでいるのか。辛くも生きのびてきた、その道をもどるための道を進まんとしているのか。ただ男の足音だけが聞こえる。
白く装われた雪の道を、男が往く。
※赤毛のアン(モンゴメリ著、村岡花子)昭和54年新潮文庫より