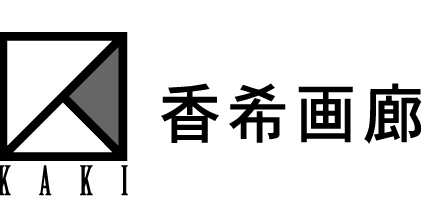Art Column

第12回「花の記憶」
いつの間にか百花繚乱の季節が過ぎ、気がつけばもう夏の気が立ちはじめている。木立の葉は日毎にみどりを濃くし、強風に動いて時に怪しい気配さえ漂わせている。若葉の時期もとうに終わったというのに、三月に母を亡くしてから、私は標ない道をひとり歩いている感覚から抜け出せずにいる。ぼんやりと自室のルドンのリトグラフを眺めたりしている。
「L'ART CÉLESTE」日本語で「天上の芸術」と題されるこの作品には、ビオラだろうか楽器を弾きながら天空を遊歩している、哀しげな表情の天使が描かれている。天使の遥か視線の先にあるのは竪琴か。手前の横顔の男の目には、一体何が映っているのだろう。長らく眺めてはいるが、いまだに絵から天使の奏でる音楽は届かない。モノクロで音のない世界が遠く彼方に広がっている。
ある朝近所の方が芍薬を届けて下さった。丹精込めて育てられた大輪の花に、生々とした蕾がまだふたつ付いているのが嬉しい。思わず綺麗と声をあげたら、「お宅には色がないからねぇ」と芍薬のご婦人は画廊の玄関周りを一瞥して仰った。入り口手前のショーウインドウに作品が1点と、玄関脇に山法師を植えている。山法師は今年花をつけなかった。画廊の外観はソリッドな雰囲気にと言えば聞こえはよいが、色気の無い主人を含めて、色が無いと言われれば、さもありなんと思う。
コロナの時期を経て久方ぶりにお会いしたご婦人は、今年卒寿を迎えられたとの事。婦人に母の面影を重ねた。早速頂いた芍薬を仏前に供えてふと思った。人は色に希望を見出すのかと。
オディロン・ルドンの作品に「黒の背景の大きな花束」というパステル画がある。あるコレクター邸で見たこのパステルの花の美しさが忘れられない。花がパステルになったのか、パステルが花になったのかと、夢幻の花の美しさに思わずため息がこぼれた。
長い間「黒」に没頭し、色彩から離れて制作していたルドンだが、晩年色彩の世界に戻り、花を主題とする作品を数多く描き始める。
ルドンの手にかかると、晴朗な自然の中に咲く花々が、突如としてひとつの音楽に導かれるように色を重ね合い、天上的なものへと高められてゆく。花は花を超え、恍惚とした美しさを醸し出し、観る者をして此岸と彼岸が交感する不思議な世界へと誘う。
花の背景に黒が使われている作品は存外少ない。その絵は背後の黒が花に燐光のような光を放たせていた。その光に刹那に蘇る命をみた。色はまさに魔法と化した。
数年前、木も生えない高度の山を友と歩いた。鳥も人もいない、音のない山。微かに風は吹いていたのか。歩を進める足音だけが、自然と自分達との境界を知らしめる。歩みを止め、見れば群生した花が風にそよいで一斉に手招きをしている。音のない景色に佇み、花の色に浸った。黄色の無数の花が、無音のうちに音楽を奏でているようであった。浄土とはこんなところかと、ふいにそう思った。
彼岸へ旅立った母の思い出が、忙しなく再生されるビデオのように、日々私の記憶の中でスローとサーチを繰り返し、スキップしてはまた元に戻る。思い出はあまりムキになって確かめないほうがいいらしい。しばらくはそのまま未来に残しておくことにしよう。
咲かないとあきらめていた芍薬の、二つ目の蕾も、今日になって花開いた。