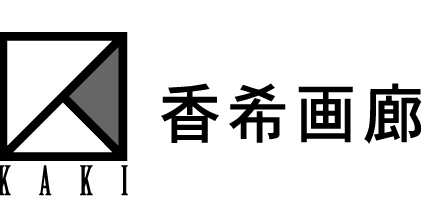Art Column

第13回 「八木の小壷」
初夏の恒例となった山歩き。昨年は雨に悩まされたが、今年は梅雨入り前から真夏のような日が続き、暑さを警戒して出発時間を早め午前中に下山、友人の家でランチをご馳走になった。気遣ってセットしてくれたテーブル席から隣室に掛けられた「清濁」の書が見えた。友人の亡き父上は、書家であった。
夕方に近いとはいえ、明るいうちに戻った自宅も暑い。生けた花がすぐ傷む。卓上の小さな写真立ての母に、花がないのはさみしい。何か飾りたいと考えてふと、あれがあるじゃないと、テレビのCMで聞いたような呟きと共に押入れを開けた。何年も仕舞い込んでそのままにしていた、高さ10センチ程の陶の白い小壷。模様は無いかわりに、胴の部分に小さく「母」と一文字入っている。小壷の作者は八木一夫※1、「母」と書いたのは今東光だと、店主が言った。どんな縁で八木の小壺に東光が「母」と書いたのか、何故「母」なのか、勝手に想像してみるのも一興と求めたものだった。
八木の小品は画廊にも数点あるが、どれも細部に緊張感を宿す。轆轤さばきが気持ち良く、造形の清潔さが好ましい。それらを手に取る度に、八木が随筆の中で語った言葉が思い出される。
「美しさは背負っていくものではない。落としていくものだ。醜を背負いつづけていくには勇気がいる。」
忘れられない、忘れる事を許さない八木の言葉である。
「陶家随想」※2と題されたその随筆は、貧しい暮らしのなか、歳暮用にと頼まれて八木が何百個か作った注文品を、後に絵描きである友人が古道具屋で見つけ出してきたエピソードから始まる。世の名工たちが凡作を叩き割って日の目に曝さないようにする行為を、八木は潔いと言えばそうだが、不出来を隠す事と同じではないかと批判する。そして作家本人にとって、また第三者にとっても、その行為がどういう意味を持つのかと懐疑する。作った時の自分の真相が作品に現れるという意味において、秀作といわれるひとつも、その他多くの凡作も、すべてを等価とする考えに八木は立っている。
音楽にも文学にも秀でた才能の持ち主だったと言われる八木は、しかし、陶芸においてしか語り得ない美を追究した。手で土を触り、手を媒体に感情や情趣を土に移し、土を陶へと変えて行く。ごまかしのない、偽物でないほんとうの何かを現したいと、あるいは現れると信じて、八木は仕事をしたのだ。あくまでも正直に仕事に勤しむ中で、美は恵みとして、たまさか与えられるものであると、作ることの意義をそこに見出した。
手仕事によってもたらされた作品そのものに内在する、自身の意図する、否、意図を超えた美に、八木は出会いたかったのだと思う。
八木にとって美は恩寵であった。
さて、私の小壺もおそらく、八木が日々の生活の糧を得るために作った何百という注文品の中の一つだろうが、それはけっして痩せてはいない。うまさに乗じて軽くあしらったという不真面目さがない。数仕事で荒れた恥ずかしさがなく、堂々としている。
小壷は、これからの私を見て居てくれるだろうか。人生に数えきれないほどある上りと下りを、いつかともになつかしんでくれたなら、嬉しい。下山は次の登山の準備と助走だと気持ちを整えて行こう。
母の霊を慰めようと供えた八木の小壷は、そのまま私への慰めとなった。
※1 1918年、京都五条坂の陶工の長男に生まれた。実用的な器物づくりから離れ、彫刻的な作品で純然たる造形表現を追求した。オブジェ焼きの創始者。30歳で前衛陶芸運動体「走泥社」を結成。1979年心不全のため急逝。享年61歳。陶芸の新しい可能性を開拓し、没後40年以上経った今もなお、世界の耳目を集める陶芸家。
※2 1982年に作品社から出版された日本の名随筆、テーマ別に全100巻あるうちの5「陶」に掲載。